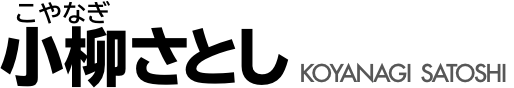福島潟自然文化祭で花火があがりました「ここ華プロジェクト」
にいがた北青年会議所の9月事業として福島潟自然文化祭にて花火をあげさせて頂きました。
実現に至るまで関係各所との調整に1年近くの時間が必要となりました。以前にも青年会議所として花火をあげる動きがありましたが、関係各所との調整が整わず実現できなかったと伺いました。
豊栄青年会議所の原点は福島潟
福島潟はにいがた北青年会議所(旧豊栄青年会議所)の運動の原点です。41年前、豊栄の青年が青年会議所を立ち上げ、その運動の中心が当時まだ注目されていなかった福島潟でした。今でこそビュー福島潟、遊水館、菱風荘、潟来亭などこどもから大人まで、そして北区以外の方が多く訪れる場所となりましたが、当時はそういった施設もなく、地元の住民の皆さんが訪れるような場所でなかったと伺いました。
そこで旧豊栄青年会議所が運動を展開し福島潟の将来像について絵を描き機運を高め、結果的に多くの施設が建設され北区を代表する観光スポット、野鳥といえば福島潟と言われるまでの現在の姿になったと伺いました。福島潟自然文化祭では今でも多くの方が福島潟を訪れ、地元の葛塚中学校の生徒、葛塚東小学校の児童が地域の文化を理解する機会として活用されています。中学校生徒と地元住民とで一緒に設置する雁迎灯(かんげいび)は今ではオオヒシクイを迎える前の福島潟の代表的な風景となりました。
注目が集まる福島潟
近年インバウンド需要の増加もあり福島潟の可能性に注目が集まっています。新潟市の中心部から車で30分、新潟空港からも近くアクセスがいいこと、月岡温泉など周囲の観光施設との近接性、なんといっても福島潟の貴重な動植物、日本の原風景が今も残っている点が多くの観光客も注目を浴びています。ザリガニ、雷魚など福島潟でとれるものを使った潟料理も地元の料理人さんにより登場しました。
一方で地元住民にとっての福島潟の存在感はあまり変化がないように感じます。私もその一人です。小学生の頃にプール利用のため福島潟周辺によくいきましたが、大人になり新潟にUターンしてから行くことはまれでした。青年会議所に入会して12年になりますが、青年会議所の運動で毎年福島潟自然文化祭にブースを出すのが一年で唯一の機会であった年もありました。
福島潟に新たな光を
そんな中、2025年はにいがた北青年会議所の理事長をさせていただく機会に恵まれました。一年間、どのように地域に根差した活動をしていくのか?青年会議所の運動を展開していくのか考えた時に、原点である「福島潟」に焦点を当てたいと考えました。そして、地元に住む我々が福島潟に足を運ぶ機会を作りたいという気持ちと、新たな可能性を探るため、思い切った事業、賛否両論が起きるような事業をしたいと思うようになりました。テーマは一点突破です。
IT技術が発達し誰でも発信できる時代、自由な時代になりました。一方で閉塞感が漂う現代です。常に誰かから監視されているような、そんな窮屈な時代です。そんな時代だからこそ、閉塞感を打破するような運動、姿を提示する団体が青年会議所でありたいと強く思いました。そこでこの度、福島潟で花火をあげる事業の計画がスタートしました。
経済か環境かの二項対立を超えて
「福島潟で花火なんてとんでもない」「福島潟は観光地でない」そういったお声があるのも承知しています。一方で、地元自治会の方からは、「思い切った事業で多くの人に福島潟に来てもらい盛り上げて欲しい」との声も頂きました。
必ずしも声は1つではありません。立場、年齢、人生経験、価値観も違えば考え方、感じ方は様々です。
新潟市は2022年のCOP14でラムサール条約湿地自治体として日本で初めて認証されました。
潟だけではなく、川、田んぼなど新潟市内の湿地で、地域住民などが賢明な利用を進めていることが世界に認められたことによるとのことです。「地元住民の賢明な利用」というのがポイントだと私は感じました。ラムサール条約に認定されれば一切手出しできないというのは誤りで、地元住民の賢明な利用あってこその湿地、潟であるはずです。
福島潟も初めから今の形があった訳ではなく、地元住民が暮らす中での水との戦いがあり、干拓、放水路、堤防の整備などがあり今の形になりました。暮らし、文化と福島潟は切っても切り離せません。今回の花火がそういったことを考えるきっかけの1つになればとの思いもありました。地元住民にとって福島潟はどんな場所であるべきか?これからあるべきか?
福島潟で花火あがる
今回は福島潟自然文化祭のイベントの最後ににいがた北青年会議所主催で花火事業を実施しました。環境団体との調整等もあり打ち上げ時間を短くすること、打ち上げ場所の調整など、打ち上げに至るまでたくさんの出来事がありました。花火の規模は決して大きいものではなかったかもしれませんが、手作りのここにしか咲かない華を咲かせることができました。
ご協賛いただいた地元企業の皆様、応援いただいた地元自治会の皆様、当日手伝ってくださった皆様、自然文化祭実行委員会の皆様、そして一緒に計画から当日の片付けまで一緒にやり切ってくれたにいがた北青年会議所の仲間、皆さんには感謝しかございません。
0から1をつくることはとても難しいことですが、だからこその楽しみもあります。1を作ったから見えてきた課題もあります。いただいた声は、評価する声もそうでない声も真摯に受け止めたいと思います。
その上で今回の1が我々地元住民にとって福島潟との新たな関わり合い、我々自身がこれからの福島潟とどう付き合っていくのか考えるきっかけになることを強く願います。